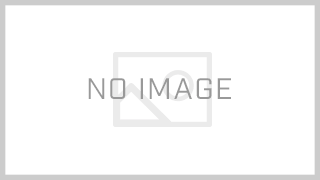本書は、フランスのトイレに関するすべての疑問に答えていると言わないまでも、どこに問題があるかを明らかにし、そしてその問題を解決するためにフランス人がこれまでどのような努力をし苦労をして来たかということを豊富な資料を用いて時代順に叙述しています。
中世フランスのトイレ事情
私たちが生まれてから死ぬまでついて回るのが排泄という行為。この本はトイレにまつわるさまざまなことを解き明かします。世界のファッションのリーダー的存在であるあのフランスでは、かつて建物の窓から汚物を通りに捨てていました。通りを歩くときはいつ汚物が降ってくるか分からないので、傘なしでは歩けなかったそうです。
われわれが住居の完全な見取り図を参照できるようになるのは十六世紀以降のことで、この頃から建築に関する記述も多くなります。そして、中世の便所は-その後の改築などですべて消えてしまったのだが-住居の中心部に位置していたことが多いのです。
しかし、この頃から人々は便所を隔離しようと望むようになります。哲学者かつ社会改革者であったジャン=ルイ・ヴィヴェースはその『対話』の中である家を描写し、用便所はその臭気のために屋根裏に置かれ、家族は各々の部屋で壺を用いると書いています。
フランソワ一世によってフォンテーヌブローに招かれたイタリア人建築家セルリオはその大著の中で様々なタイプのフランスの住居を書いています。それらは便所を最上階や庭の中に隔離しようとするこの新しい欲求をはっきりと表しています。時に、嘆かわしい方策ですが、料理場の隣に置かれた場合もあります。
羞恥心、価値観の違い
日常生活において便器や用便所を苦労して探すような人間は一人もいなかったし、手本は高貴な社会が示していました。フュルティエールの伝えるところによると、王妃アンヌ・ドートリュッシュの侍従であったブランカース伯爵はある日王妃の手を離すと壁のタピスリーのところへ行って放尿したといいます。恥じらいという語は十七世紀にはほとんど意味を持っていなかったわけです。
おまるは非常に便利ではあったが、たとえ椅子の上に置かれてもそう心地よいものではなかったそうです。そこで十七世紀には既にそれ以前から王家で愛用されていた美しい高級家具、穴あき椅子が普及することになります。
ルイ十四世時代のヴェルサイユ宮殿の財産目録には二七四脚の用足し用の椅子が記載され、その内の二〇八脚は下に受け皿を持っただけの簡単なもの、六十六脚が引き出し付きで、受け皿は密閉された引き出しの中に格納されています。
ルイ十三世が既にこの玉座に腰掛けて接見していたことは知られています。タルマンによると、王の道化師マレーがある日王に言ったという、《陛下のお仕事で私めがどうしても真似のできそうもないことが二つございます。-それは何じゃ?-たった一人で食事をすること、人の前でうんこをすることでございます。》その息子ルイ十四世も同じように振舞ったそうです。
1885年7月、市当局の代表者の一人であるブールヌヴィル医師が下院に提出した報告書には次のように書かれています。
《セーヌ河は右岸沿いでは正真正銘の蓋なしの下水である。水は濁り、色がつき、油ぎった泡に覆われている。酸素は腐敗進行中の有機物にほとんど完全に吸収されて存在しない。夏期には常時起こる発酵のために河の水は泡立ち、底の汚物が表面に浮かび上がり、時に直径一メートルにも達する巨大な泡となって沼沢性ガスが発生する。河岸には黒ずんだおりがべっとりとついている。幹線の開口部では砂や他の重い物質が黒く悪臭を持つ巨大な泥層を成し、その厚さは〇・六五メートルから三メートルまでになり、これらの開口部からマルリーまで延びている。》