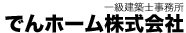今、注文住宅での家づくりを考えている人は一度は聞いたことがあるかもしれない言葉「高気密高断熱住宅」。
昔の木造住宅は「夏暑く、冬寒い」家だったわけですが、現在の木造住宅でハイスペックな家は「夏涼しく、冬あたたかい」家になっています。
一年通して、年中快適な家というわけで、その快適さが知られるようになると、評判になり、「高気密高断熱住宅」がメジャーな存在になってきています。
その「高気密高断熱住宅」、その誕生から普及の立役者は、鎌田紀彦さんという方であり、一般的に「新住協(新木造住宅技術研究協議会)」という組織なのです。
今回は「新住協(新木造住宅技術研究協議会)」という組織、そして、鎌田紀彦さんが行ってきた「高気密高断熱住宅(高断熱・高気密住宅)」の開発から普及の歴史も合わせて解説していきます。
外部リンク:新住協(新木造住宅技術研究協議会)公式HP
ざっくりとした新住協(新木造住宅技術研究協議会)の沿革
一般社団法人 新木造住宅技術研究協議会 理事の 鎌田紀彦さん(室蘭工業大学名誉教授)。鎌田紀彦さんは1977年に東京大学大学院博士課程を修了した後、1978年に室蘭工業大学建築工学科助教授に就任します。
着任後、北海道の木造住宅は当時、断熱材が入っていない、なんと無断熱状態だったそうです。灯油の消費量が大きく、その後、1984年(昭和59年)に断熱気密性能を向上させる在来木造改良工法を考案しました。
1987年(昭和62年)に「新在来木造構法」としてマニュアルを作成、同時に「高断熱・高気密住宅」と名付け、暖房エネルギーを増やさずに全室暖房の快適性を実現する省エネルギー住宅を提案しました。
この提案に応じるかたちで、1989年(昭和64年)に発足したのが「新在来木造構法普及協議会(新在協)」で、1995年に「新木造住宅技術研究協議会(新住協)」になります。高断熱・高気密住宅の普及促進とさらなる技術開発を目指しました。
2005年(平成18年)に、北海道で暖房負荷を一般住宅の半分以下で全室暖房を可能にする「Q1.0住宅(キューワンじゅうたく)」を提案しました。名前の由来は、この住宅のQ値がちょうど1.0前後になるからです。
2011年(平成23年)に新たに省エネ基準住宅の40%-55%以下の暖房負荷で全室暖房を可能にするQ1.0住宅レベル-1と、更に高性能化するQ1.0住宅レベル-2、レベル-3、レベル-4を日本全国で定め、提案しました。
新住協の会員には、全棟Q1.0住宅レベル-1以上の性能の住宅を建設するよう呼びかけました。
新住協は「全棟Q1.0住宅レベル-3以上の住宅建設を実現する」ことに目標を変更して、日本の快適・高性能・省エネ住宅建設の先頭を走る感じになります。
これまでの主な研究開発(新住協から生まれた技術)
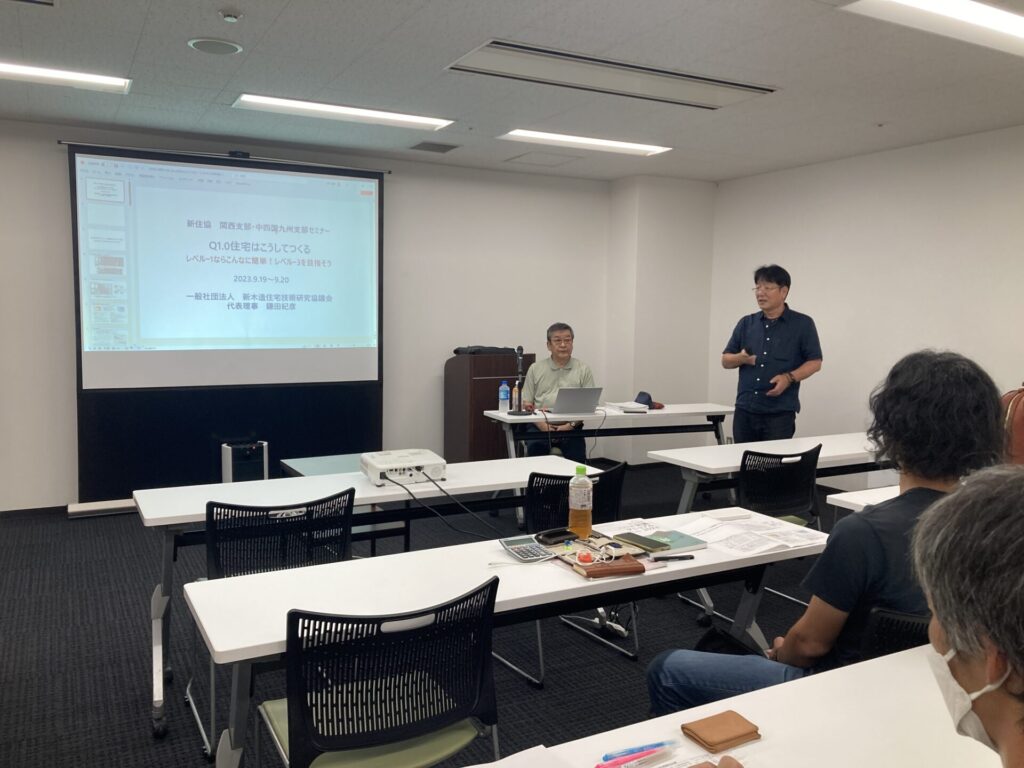
- 防湿シートを気流止め・気密層とする高断熱工法(シート気密工法)
- 床・外壁の下地ボードを気密層とする高断熱工法(ボード気密工法)
- 透湿防水シートを使った通気層工法
- 床・壁・天井・屋根のグラスウールによる厚い断熱工法
- 燃費半分以下で快適に暮らせるQ1.0住宅
- 暖冷房エネルギーを計算できるQPEXプログラム
- 在来木造の柱梁表しの同面真壁工法
- 既存住宅のローコスト断熱・耐震同時改修工法
- 床下を利用するエアコン1台の快適冷暖房システム(床下エアコン)
- FFストーブや温水による快適な床下暖房システム
- 高断熱住宅の夏を涼しくする住宅設計手法
- 熱交換換気システムの住宅への導入と改良
「高気密高断熱住宅(高断熱・高気密住宅)」の開発から普及の歴史

北海道でさえ、木造住宅に断熱材が使われだしたのが昭和40年代前半だそうです。
オイルショックの昭和48年までは北海道で新築住宅の20%くらいが灯油ボイラーによる温水セントラルヒーティングをはじめたそう。「北海道は寒い世界ですから、何としても暖かくしたい」と。その住宅が灯油をどれくらい消費したかというと、ざっと5,000リットルから7,000リットル。1リッター30円くらいだったので、多くいっても20万円くらい。当時としてはお金持ちなら、払ってもいいかなと思えるレベル。
ただ、これがオイルショックで1リッター80円ぐらいまで上がりました。1年で50万円前後。当時の大衆車でトヨタがパブリカという車を出していたのですが、これが1台50万円。要するに車1台買えるっていうことで、みんなセントラルヒーティングをやめにして灯油ストーブ暖房に戻って、そして2,000リットルぐらいで寒いのを我慢して暮らしていたそうです。
そうこうしているうちに、木造住宅に断熱材が使われだしたことから、新築住宅の床が2-3年でどさっと抜け落ちるというナミダダケ事件というのが起きました。
これは大体北海道内で1,000戸ぐらいの住宅が被害を受けました。床を全部剥がして地面を全部消毒して、もう一回床を作り直して、でも、また2、3年で腐るんだそうです。高気密高断熱住宅の初期の話です。トラブルもあったわけです。
断熱材の厚みは昭和45年ごろ、50ミリ断熱で、床・壁・天井50ミリくらいのグラスウール10kg断熱材を入れていたそうです。
北海道で断熱材が入った住宅が売れた理由
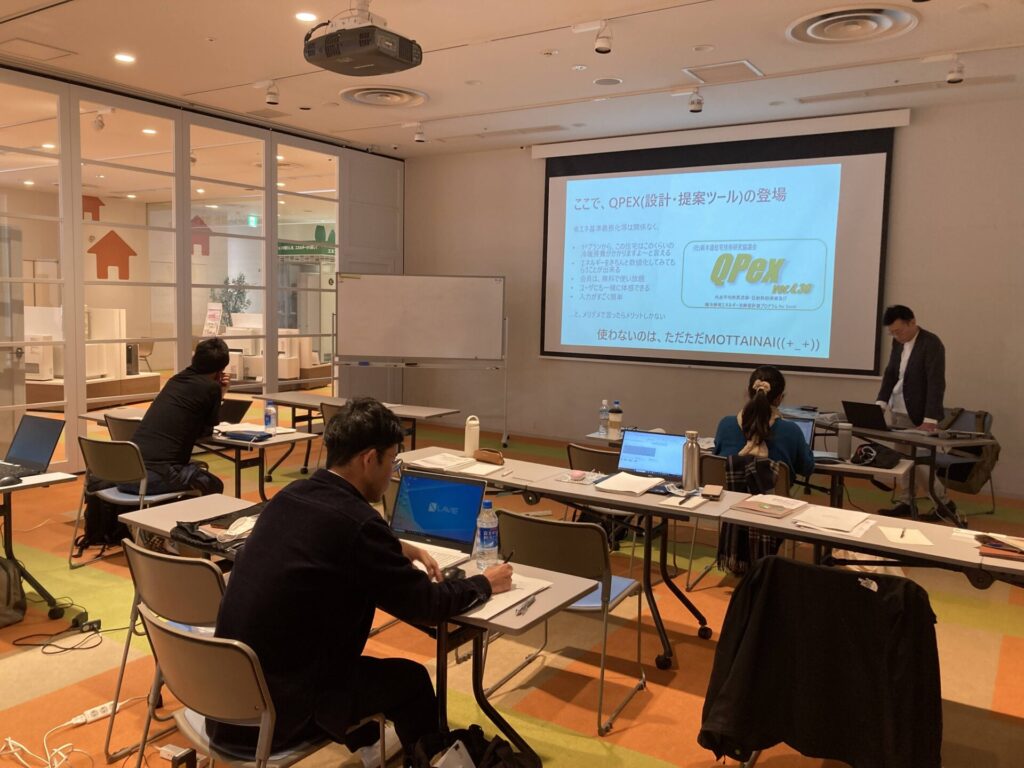
元々、北海道では住宅金融公庫はブロック造の住宅にしかお金を貸さなかったそうです。それを木造住宅で断熱材を施工した住宅にも貸すよとなったのが、昭和45、6年だそうです。そうすると住宅が買いやすくなって売れていくわけです。
断熱材はどんどん普及していって、オイルショックの間に壁が100ミリ、天井200ミリ、床200ミリの厚みくらいになります。ざっと、2倍から2.5倍くらいの断熱材を使うようになったのですが、実は暖房エネルギーも減らないし、部屋のなかも温まらなかったそうです。
昔は灯油を5,000リットルから7,000リットル使っていたのが、調査すると、昭和57、8年頃、寒地建築研究所が札幌・旭川で灯油消費量調査をしまして、50ミリ断熱の住宅、100ミリ断熱の住宅でセントラルヒーティングをしている住宅を調査してみると、まだ5,000リットルから7,000リットル消費していたそうです。
昭和52年に鎌田紀彦さんが室蘭工業大学に着任。
現場調査や大学内に実験棟を建てるなどして研究。壁のつくりを45cm幅ずつ色々な作り方でしてみて、中が結露するとかしないとかの検証をしていくうちにだんだんと様子がわかってきます。
まず、壁の中に床下から空気が入ってくるのが結露の原因であり、断熱材が効かないすべての原因であると発見したのです。
1984年に札幌郊外に住宅供給公社の住宅をお願いして、2棟建てるうちの1棟を鎌田紀彦さんの改良方法で建てて、1棟は今までの普通のやりかたで建てる。断熱材も一緒、窓も一緒、ストーブも同じものがついてて、間取りも同じ。今まで通りだと、普通に灯油2,000リットルかかって、寒い。それが改良方法で建てた家は家じゅう快適になっていて、灯油消費量は大体1,200リットルぐらい。
その結果をハウスメーカーや工務店を集めて200人ぐらい集まったところで研究発表会をしました。北海道で150社、秋田や新潟、本州の会社も50社くらい。そこから始まりました。
「新住協(新木造住宅技術研究協議会)」のはじまりです。
日本の住宅で断熱材が使用されるようになったきっかけは「住宅金融公庫の融資(住宅ローン)」
昭和54年に住宅金融公庫の融資(住宅ローン)、今でいう「フラット35」の融資で仕様書に断熱材を必ず施工しなくてはいけなくなりました。これが日本の断熱材、日本中の断熱施工の始まりです。
当時、東北・北海道だと8割から9割が住宅金融公庫の融資(住宅ローン)だったそうです。金利の高い頃ですから、あの頃、住宅の貸付金利は6%とか7%、そこに住宅金融公庫が5%で貸すということで、みんな借りたわけです。
次世代省エネ基準で日本の住宅が高断熱・高気密住宅に向けて動き出す
平成11年に次世代省エネ基準ができました。解説書のなかで「高気密高断熱住宅」という言葉が出てきて、日本の住宅が高断熱・高気密住宅に向けて動き出すことになります。
高断熱・高気密住宅は一般住宅の暖房費を増やさずに、快適で健康的な全室暖房の生活が送れるようにしましょうという提案だったわけです。
ただ、次世代省エネ基準で建てて全室暖房をやると、暖房費が1.5倍から2倍と増えてしまうことになります。なので、これはマズいと、新住協は考えました。
北海道では一般住宅より少ない金額で全室暖房ができていたので、一般住宅の半分以下で全室暖房ができるようにしようというのが「Q1.0住宅(キューワンじゅうたく)」のはじまりです。
そこからQ1.0住宅レベル-1、レベル-2、レベル-3、レベル-4と提案していっています。
Q1.0住宅レベル-1は省エネ基準住宅の40%-55%以下の暖房負荷で全室暖房を可能にするレベル。
Q1.0住宅レベル-3は省エネ基準住宅の35%-20%以下の暖房負荷で全室暖房を可能にするレベルです。
2023年10月から、「全棟Q1.0住宅レベル-3を目指そう」と更に強力にレベルアップした目標を打ちだし、取り組んでいくことになりました。






「家づくりって、どうすればいいの?」「家づくりの基本は2つだけ」「地震で壊れる家、壊れない家の違いは何ですか?」「地震で壊れない家を建てるには?」「夏涼しく、冬あたたかい住まいにする方法」「断熱材について知っておくべき2つのポイント」「住宅ローン、借りられる人、借りられない人」「ブラックリストに載ると、住宅ローンNG?」「住宅ローンは固定金利・変動金利。どちらがいいか?」・・・
こんなことを無料でお伝えしています!
・好きな時間に家づくりの知識・ノウハウが得られます
・どこかに出かけなくても、情報収集できます
・変な売り込みを直接かけられずに、家づくりの話が聞けます
・登録も簡単。解除も簡単。無料です。
ご登録は以下のフォームから!